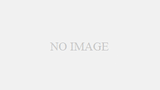「親が多額の借金を残して亡くなった」「遺産を相続したくない」といった状況に直面したとき、「相続放棄」という選択肢が頭に浮かぶかもしれません。しかし、自分が相続放棄をすると、その影響が子どもや孫にまで及ぶのではないかと心配になる方も多いのではないでしょうか。 この記事では、相続放棄の基本的な知識から、多くの方が疑問に思う「代襲相続」との関係、特に子どもや孫への影響について、わかりやすく解説します。相続放棄の手続きや注意点もあわせてご紹介しますので、ご自身の状況と照らし合わせながら、最適な選択をするための一助としてください。
1.相続放棄の基本:子どもへの影響を考える前に
相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)が残した財産を一切受け継がない意思表示のことです。これには、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。つまり、相続に関するすべての権利と義務を放棄することになります。
相続放棄が選ばれる主な理由は以下の通りです。
- マイナスの財産(債務)が多い場合:被相続人の借金などマイナスの財産を引き継ぎたくないケースが最も一般的です。
- 相続争いを避けたい場合: 他の相続人とのトラブルに巻き込まれたくない場合に利用されます。
- 特定の相続人に財産を集中させたい場合: 家業を継ぐ一人に財産をまとめたいときなどにも使われます。
家庭裁判所で相続放棄の手続きが認められると、その人は法律上「初めから相続人ではなかった」ものとして扱われます。
2.代襲相続とは?相続放棄との違い
次に、代襲相続について理解しましょう。代襲相続とは、本来相続人となるはずだった人(例えば、被相続人の子)が、相続が始まる前に亡くなっていたり、特定の理由で相続権を失っていたりした場合に、その人の子ども(被相続人から見ると孫)が代わりに相続する制度のことです。
代襲相続が発生するのは、法律で定められた以下のケースに限られます。
- 相続人が相続開始前に死亡している
- 相続人が相続欠格事由(重大な非行などにより相続権を失うこと)に該当する
- 相続人が相続廃除(被相続人の意思で相続権を奪われること)をされている
ここで最も重要なポイントは、この代襲相続が発生する原因の中に「相続放棄」は含まれていないという点です。
3.相続放棄は子や孫の代襲相続に繋がらない理由
結論から言うと、親が相続放棄をしても、その子ども(被相続人から見た孫)が代わりに相続する代襲相続は発生しません。つまり、「相続放棄をすると、自分の子どもや孫に借金が引き継がれてしまうのでは?」という心配は不要です。
なぜなら、相続放棄をした人は「初めから相続人ではなかった」とみなされるためです。相続人ではない人の子どもが、その人の代わりに相続するということは起こり得ません。したがって、子が相続放棄をすれば、その孫が相続人になることはないのです。
4.相続放棄が他の家族(子ども・孫以外)に与える影響
相続放棄をすると、代襲相続は起こりませんが、他の親族に影響が及ぶ可能性があります。主な影響は2つです。
1. 他の相続人の相続分が増える
同じ順位の相続人が複数いる場合、一人が相続放棄をすると、その人の相続分は他の相続人に分配されます。例えば、相続人が配偶者と子ども2人で、子どもの1人が相続放棄をした場合、放棄した子はいなかったものとされ、配偶者と残りの子ども1人が財産を相続することになります。
2. 次の順位の人へ相続権が移る 同じ順位の相続人全員が相続放棄をした場合、相続権は次の順位の相続人に移ります。相続人の順位は法律で決まっています。
第1順位: 子(子が全員放棄すると、孫ではなく第2順位へ)
第2順位: 直系尊属(父母、祖父母など)
第3順位: 兄弟姉妹
例えば、子どもが全員相続放棄をすると、次に被相続人の父母が相続人になります。父母もすでに亡くなっているか相続放棄をすると、今度は被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。このように、相続放棄は自分一人の問題だけでなく、親族全体に関わる可能性があることを理解しておく必要があります。
5.相続放棄の手続きと注意点
相続放棄をするには、家庭裁判所で正式な手続きが必要です。口頭で他の相続人に「放棄する」と伝えただけでは、法律上の効力はありません。
手続きの概要は以下の通りです。
- 期限: 原則として、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」です。この期間は「熟慮期間」と呼ばれます。
- 申述先:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
- 方法: 「相続放棄申述書」や戸籍謄本などの必要書類を提出して申述します。
6.相続放棄を検討する際には、以下の点に注意してください。
原則として撤回できない
一度、相続放棄が受理されると、後から取り消すことは原則できません。
相続財産の処分
相続財産の一部でも使ったり売却したりすると、単純に相続を承認した(法定単純承認)とみなされ、相続放棄ができなくなる可能性があります。
未成年者の手続き
相続人が未成年者の場合、親権者などの法定代理人が代わりに手続きを行います。
管理義務が残る場合がある
相続放棄をしても、次に相続人となる人が財産の管理を始めるまでは、手元にある遺産を管理する義務を負うことがあります。
7.まとめ:相続放棄は子どもや孫への影響を理解して慎重に
相続放棄と代襲相続の関係について解説しました。重要なポイントを改めてまとめます。
相続放棄をしても、その人の子どもや孫が代襲相続することはありません。
相続放棄をすると、その人は「初めから相続人ではなかった」ことになります。
相続権は、他の同順位の相続人や、次の順位の相続人(親や兄弟姉妹など)に移ります。
手続きは「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所で行う必要があり、一度行うと撤回はできません。
相続放棄は、借金から逃れる有効な手段ですが、他の親族への影響も大きい法律行為です。手続きには期限があり、慎重かつ迅速な判断が求められます。もし判断に迷ったり、手続きに不安があったりする場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。