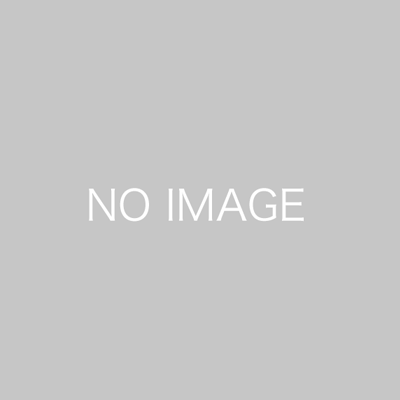任意後見制度
任意後見制度について
任意後見制度とは、本人の判断能力が不十分になる前に、判断能力が低下した後の生活を支援してくれる人を契約によって自分で定めるものです。
例えば頼れる身寄りがいないまま、将来自分が認知症になってしまったら、その後の生活はどうしていけばよいのか。軽度な判断能力の低下から、一人での生活が困難になり施設等での生活を余儀なくされた場合に、これまでの暮らしぶりや趣味嗜好を自身ではうまく伝えられなくなってしまっていたら、誰が自分のことを理解してくれるのか。
そんな不安を取り除き、最期のときまで自分らしい人生を歩むための備えとなる制度が、「任意後見」です。
任意後見人の権限
任意後見は本人の判断能力が十分なうちに、自身の意思によって任意後見契約を結びます。したがって受任者の同意は必須であるものの、違法の場合を除き、自由に契約内容を決めることができます。
つまりあらかじめ契約書に運用について記しておけば、法定後見の場合と異なり、積極的に資産を運用することも可能になるというわけです。
しかし任意後見は、財産管理の方法を自由に選択できる反面、任意後見人の権限が任意後見契約書で定めた代理権の範囲に限定されるため、任意後見人には、本人の行為を取り消す権限はありません。
そのため本人がした行為を取り消す場合や、任意後見契約書で定めた代理権の範囲を拡張する必要がある場合には、任意後見契約を終了し、法定後見に移行することになります。
ただし、任意後見が発効している最中に任意後見を終了するには、本人の利益を守るため、特に必要がある場合に限られます。
手続きの流れ
任意後見による保護を受けるには、信頼出来る人と任意後見契約を締結し、公証人役場で公正証書を作成しなければなりません。
ここではだれを任意後見人にするか、どこまでの後見事務を委任するかについて、話し合いによって自由に決めることが出来ます。
そして本人の判断能力が低下し、後見人の後見事務を監督する「任意後見監督人」が選任されたら、実際に任意後見が開始されます。
これに法的な分類はありませんが、利用形態として「将来型」「移行型」「即効型」に分かれます。
- 将来型 将来、判断能力が低下したら任意後見を開始する。
- 移行型 本人の判断能力が十分なときは、第三者が委任契約によって本人の財産を管理する任意財産管理を行い、判断能力が低下すれば任意後見に移行する。
- 即効型 任意後見契約を締結し、すぐに任意後見をスタートする
その後任意後見人は、事前に交わした契約で定められた仕事を適切に行わなければなりません。