転籍
企業において、異動や配置転換はよく行われる人事の一環で、社員に転籍を命じることも多く行われています。
本コラムでは、転籍と出向の違いや効力、会社がとるべき対応について解説いたします。
目 次 [close]
転籍とは
転籍とは、会社との現在の労働契約関係を終了させて、新たに他社との間に労働契約関係を成立させ、当該他社の業務に従事する人事異動をいいます。
そのため、就業規則は転籍先のものが適用され、指揮命令だけでなく給与の支払などの責任を持つのも転籍先となります。
転籍には、以下の2種類があります。
- 転籍元会社との労働契約の解約+転籍会社との新労働契約の締結
- 労働契約上の使用者の地位の譲渡
なお、上記のいずれの場合であっても、転籍を行うためには労働者の同意が必要となります。
出向との違い
出向とは、出向元の企業の従業員としての地位を保持したまま、他企業の事業所において相当長期間にわたり当該他企業の労務に従事させる人事異動のことをいい、現在労働契約関係にある企業との労働契約が継続する点で、現在の労働契約関係が終了になる転籍とは異なります。
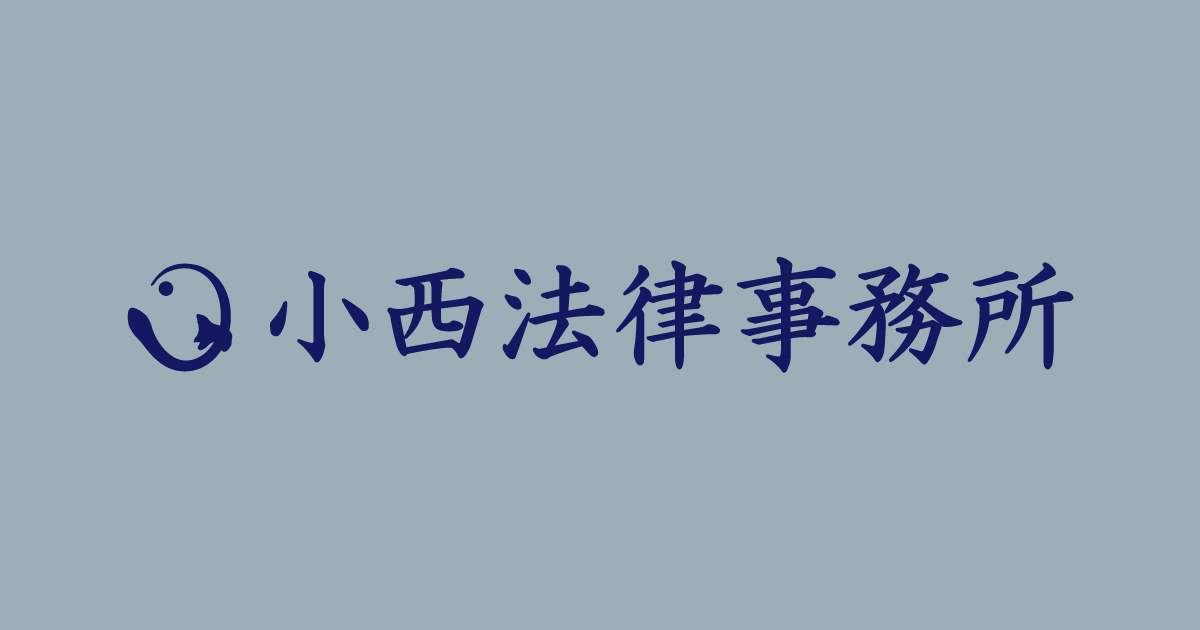
外部への社員の異動形態として様々な呼称がありますが、法的には現在の会社との労働契約関係が継続するか終了するかによって出向と転籍とに分類することができます。
また、出向か転籍かによって社員の個別同意の要否が異なりますので、注意が必要となります。
労働者の同意
原則として労働者の個別合意が必要
転籍は、出向と異なり、転籍元企業との労働契約を終了させて転籍先企業と新たな条件の労働契約を締結するものであり、労働者が職務内容や待遇など労働条件の変化により不利益を受けるおそれがあります。
そのため、転籍の際には、新たな勤務先を明示した個別具体的な同意を必要とするのが原則と解されています。
転籍は、新たな労働契約の成立を含みますので、旧使用者に対する労働者の承諾(民法625条1項)だけでは足りず、新使用者との間で労働契約を成立させる個別の合意(労働契約法6条参照)が必要となります。
労働契約を結ぶか否かは、当事者である労働者の自由であるため、労働者の個別の合意が必要となるのです。
したがって、会社は、就業規則等において「転籍を命じ得る」旨の包括的規定がある場合でも、原則として、労働者の個別の同意がなければ転籍命令をすることはできないと解されています。
包括的同意が認められたケース
もっとも、入社時などの事前の包括的同意しかない場合であっても、特段の事情があれば、例外的に社員の個別の同意がなくとも会社が転籍命令を下すことができるとした裁判例があります。
関連会社への転籍につき、会社発行の入社案内には勤務場所の一つとして当該関連会社が明記してあり、労働者が入社面接前に入社案内を読んでいること、身上調書の質問事項に当該関連会社を含む事業所での勤務の可否を問う欄があり、これに対して可に○印をつけていたこと、採用面接時に転籍することがある旨の説明に対して異議がない旨回答したことなどの事情があったため、当該関連会社に転属することにつき予め包括的な同意を会社に与えたものということができ、転属先の労働条件等から転属が著しく不利益であったり、同意の後の不利益な事情変更により当初の同意を根拠に転属を命ずることが不当と認められるなど特段の事情もないため、転籍命令が有効であると判断された事案。
日立精機事件(千葉地裁昭和56年5月25日判決・労判372号49頁)
なお、包括的同意が認められる場合であっても、転籍の目的が不当な場合などは、権利濫用であるとして転籍命令が無効とされることがあることには注意が必要です。
転籍先からの復帰
転籍先から転籍元に復帰する場合は、新たな転籍として、個別の同意が必要となります。
なお、最初の転籍の際に、復帰に関する合意をしている場合、転籍元は転籍期間終了後に労働者の復帰を拒むことはできないとした裁判例があります(京都信用金庫移籍出向事件・大阪高裁平成14年10月30日判決・労判847号69頁)。
人員削減のための転籍
転籍は人員削減のために用いられることもありますが、その場合でも、原則として労働者の個別同意がない場合には、会社に転籍命令権が認められていません。
特定部門の子会社と当該部門の従業員の転籍が行われた際に、転籍を拒否した1人を解雇したケースに関して、裁判所は、整理解雇の要件を検討し、子会社化及び転籍という施策自体には経営上の合理性があるとしても、大半の従業員が転籍に応じた以上、会社の規模、経営内容からして、残る1人を直ちに解雇するまでの経営上の切迫性、緊急性がないとし、また、会社の「転籍に応じた労働者との関係で、転籍に応じない労働者を解雇しなければ不公平」という主張を排斥した事案。
千代田化工建設事件(東京高裁平成5年3月31日判決・労判629号19頁)
営業所を閉鎖して当該営業所の業務を別会社に委ねることとし、全員解雇を行って転籍を求めたケースに関し、解雇回避努力義務違反があり、人選の合理性もなく、説明協議義務にも違反しているとして解雇無効と判断した事案。
アメリカン・エキスプレス・インターナショナル事件(那覇地裁昭和60年3月20日判決・労判455号71頁)
転籍に必要な書類
転籍は、労働者との合意のもとに契約を交わし、辞令を出して実行するものであるため、後々のトラブルを防ぐためにも、合意した内容や契約については、以下の書面で残しておくことが望ましいです。
- 転籍同意書
- 転籍契約書
- 転籍辞令
転籍同意書
転籍同意書には、転籍について従業員と話し合って合意した内容を記録し、今回の転籍について、具体的な転籍先企業名、転籍の条件、転籍日などを記載します。
<転籍同意書に記載すべき内容>
・転籍が成立したら、転籍元企業の従業員としての身分を失うこと
・転籍先企業と新たに労働契約を結ぶこと
・転籍先の基本情報(代表者、所在地など)
・転籍先で予定している役職、業務内容
・転籍先での労働条件(給与、労働時間、休日、社会保険、福利厚生など)
・転籍日 等
転籍契約書
転籍契約書には、「転籍元企業」「転籍先企業」「転籍する従業員」の三者が合意した内容を記録します。
<転籍契約書に記載すべき内容>
・転籍元企業を退職する日、および転籍先企業への入社日
・従業員の転籍先での労働条件
・退職金に関する規定 等
転籍辞令
転籍辞令は、転籍元企業が従業員に対して、転籍させる旨を通知する書類で、転籍を命じる根拠を記載することが重要です。
<転籍辞令に記載すべき内容>
・従業員に転籍を命じること
・転籍先企業及び転籍先での労働条件(転籍同意書のとおりである場合にはその旨)
・転籍元企業の名称
・転籍元企業の代表者名 等
過去の裁判例
三和機材事件(東京地裁平成4年1月31日判決・判時1416号130頁)
事件の概要
工作用機械・資材の製作・販売及び輸出入業等を営むY社は、同社の営業部門を独立させて新会社A社を設立し、Y社の営業部門の労働者全員に対してA社への転籍を内示しました。
Xを除く営業部員は転籍に同意しましたが、労働組合の書記長であったXは転籍に反対していました。
Y社は最終的にXの同意のないまま転籍命令を発しましたが、Xはこれに従わなかったため、Y社は就業規則上の「業務上の指揮命令に違反したとき」に当たるとして、Xを懲戒解雇しました。
Xは、懲戒解雇が無効であるとして、地位保全および賃金仮払いの仮処分を申し立てました。
裁判所の判断
転籍出向は出向前の使用者との間の従前の労働契約関係を解消し、出向先の使用者との間に新たな労働契約関係を生ぜしめるものであるから、それが民法六二五条一項にいう使用者による権利の第三者に対する譲渡に該当するかどうかはともかくとしても、労働者にとっては重大な利害が生ずる問題であることは否定し難く、したがって、一方的に使用者の意思のみによって転籍出向を命じ得るとすることは相当でない。
本件の場合においては、両社の間には物的な関係においても差異がないとまではいい難いうえに、Xは本件転籍出向につき具体的同意はもちろん包括的な同意もしていなかったのであるから、右同意を得ないでした会社の本件転籍出向命令は無効という外はない。
日本電信電話事件(東京地裁平成23年2月9日判決・労経速2107号7頁)
事件の概要
Y社は、平成11年の再編成により、A社、B社、C社の3つの会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有する純粋持ち株会社となりました。
Xは、昭和40年にD公社に雇用され、その後、昭和60年にD公社の民営化に伴うY社の発足により、労働契約が承継され、XはY社の従業員となりました。
Y社は、平成11年の再編成により、A社等への人員移行が不可避となったことから、再編成に先立つ同年3月、「再編成に伴う社員の人員移行等の扱いについて」と題する通達を出し、周知の手続きを経たうえで、Xに対し、同年6月24日、同年7月1日付けでA社に転籍する旨の内命を行い、Y社は、Xを含む全社員に対し、A社等の分割会社への転籍を包括発令しました。
Xはこれに同意しませんでしたが、同年7月1日、転籍後のA社の職場で業務に就き、以後、A社から賃金、賞与を受け取り、退職時にはA社から退職金を受領しました。
Xは、平成19年3月31日をもって、Y社およびA社の定年年齢に達したので、Y社の定年後の再雇用制度により再雇用されたと主張して、Y社に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認等を求めました。
裁判所の判断
本件転籍命令が有効であると言うためには、個別的な合意が必要なのはもとより、原告の明確で積極的な意思表示が必要であると解され、黙示の同意を認定することは慎重に行うべきである。
Y社は、Xが本件転籍命令により就労することになったA社の職場でXが就労し、賃金を受け取っているから、本件転籍命令に同意していると主張する。
しかし、XがA社で就労することを拒否し、あるいはA社の従業員としての服務規律に違反すれば、A社から懲戒処分がなされることは容易に想像でき、賃金を得て生活するXとしては、とりえない行動であって、これをもって、本件転籍命令に同意しているとは考えられない。
加えて、Y社は、平成11年8月から平成16年5月までの約5年間、Xが本件転籍命令について、Y社に対し異議を述べず、A社から賃金を受け取っていた等と主張する。
しかし、Xが、平成11年及び平成12年にA社に提出した自己申告表には、本件転籍命令に同意しない旨明らかに意思表示していた。また、Xは、A社に対し、平成13年8月及び12月には団体交渉申入れをし、その後、XのY社に対する復籍を主張していた。これらの事実に、XがY社に対し、従前から本件転籍命令には同意できない旨明確に述べていたこと、Y社がA社の持ち株会社であることを合わせ考えると、仮に、XがY社に対し、約5年間にわたって直接本件転籍命令に対し異議を述べていなかったとしても、Xが本件転籍命令に同意していたとは認め難い。
他方、Y社の再雇用に関する就業規則の定めは、高齢法9条1項2号の趣旨にしたがって解釈されるところ、同法が求めているのは、継続雇用制度の導入であって、事業主に定年退職者の希望に合致した労働条件での雇用を義務付けるものではなく、事業主の合理的な裁量の範囲の条件を提示することも許容されると解すべきである。
そして、Y社には、当時、Xが勤務可能な就業規則80条2項の「業務」は存在しなかったと言わざるを得ない。
以上によれば、本件転籍命令は無効であるが、Xがキャリアスタッフ制度の適用により再雇用されたとは認められない。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。

弁護士 岡田 美彩
- 所属
- 大阪弁護士会
この弁護士について詳しく見る


 前の記事へ
前の記事へ